
【実践ガイド】「ただ導入するだけ」では失敗する。Zoom Phoneを社内に定着させるための3つの秘訣
2025/06/30
目次
導入だけで満足していませんか?〜「定着しない」ツールの共通点〜
「Zoom Phone、導入したはいいけれど、使っているのは一部の部署だけ……」
このような悩みは、決して珍しいものではありません。
私たちが現場でよく耳にするのは、次のような“ツール導入の落とし穴”です。
- 導入時の説明会には参加したが、その後マニュアルは誰も読んでいない
- 業務に直結しないと判断され、使うのが後回しにされている
- 「詳しい人に聞けばいい」と考え、自ら触ろうとしない社員が多い
- 社内に使い方を説明できる人がいないため、質問がすぐ情シスに集中する
つまり、「導入=ゴール」と捉えてしまうと、ほぼ確実に“定着しないツール”になってしまうのです。
実際、クラウドPBXやコミュニケーションツール、グループウェアなど
「便利なはずの社内ツール」が現場で使われなくなるケースは少なくありません。
理由は明白です。ツールそのものに問題があるのではなく、
「導入後に、社内でどのように活用されるか」の設計と支援が不十分だからです。
導入直後こそ社員の関心は高まりますが、初期設定でつまずいたり、
活用イメージがわかないまま時間が経てば、次第に利用頻度は落ちていきます。
その結果、「いつの間にか一部の人だけが使うツール」になってしまい、
情シスや管理部門には「また使われないツールを導入した」との烙印が押されてしまうのです。
こうした事態を避けるには、ツール導入を“インフラ整備”として捉えるのではなく、
「社員の行動変容を促すチェンジマネジメント」として設計することが求められます。
図:Zoom Phone導入後によくある“使われないツール化”の兆候
次章では、なぜツールが定着しないのか、その背景にある3つの失敗要因を分解しながら、
Zoom Phoneの定着を成功させるための具体的なアプローチをご紹介します。
なぜ“定着しない”のか?失敗の原因を3つに分解する
Zoom PhoneのようなクラウドPBXや社内ツールを導入したにもかかわらず、「結局使われなかった」というケースは少なくありません。
その原因はツール自体にあるのではなく、導入から定着までのプロセスに課題があることがほとんどです。
私たちが多くの企業現場を支援してきた中で見えてきた、“定着しない3つの共通要因”を紹介します。
① 導入目的が社内に伝わっていない
「なぜこのツールを入れるのか?」「どんな業務がどう変わるのか?」という目的や期待が、現場に共有されていないケースが非常に多くあります。
その結果、「情シスの方針だから」「とりあえず従うけど使い方はよく分からない」といった受け身の姿勢が蔓延します。
背景・狙い・使うことで得られるメリットが腹落ちしていない限り、ツールは“使わされるもの”で終わってしまいます。
② 一斉導入で混乱が広がる
「来月から全社でZoom Phoneに切り替えます」——このような進め方は、実は最も失敗しやすいパターンです。
現場にとっては業務が止まるリスクとなり、「だったら旧来のやり方のほうがラク」と感じさせてしまいます。
段階的な導入やパイロット展開を行わず、一気に切り替えることで、“使えない人”を置き去りにしてしまうのです。
③ 導入後の支援が不十分
導入直後は社内でも話題になりますが、そのタイミングを過ぎると一気に関心が薄れていきます。
よくあるのは、「マニュアルはあるけど誰も読まない」「質問の窓口がなく、情シスに集中して疲弊する」といった状況です。
“使い始めたあとの困りごと”にすぐ対応できる体制がないと、ツールは“使われないまま忘れられる存在”になってしまいます。
これら3つの要因が複合的に絡むことで、「せっかく導入したのに結局元に戻ってしまう」…という残念な結果を招いてしまうのです。
次のセクションでは、こうした失敗を避け、Zoom Phoneをしっかり社内に根付かせるための実践的な3つの秘訣をご紹介します。
社内定着のための3つの秘訣とは?
では、Zoom Phoneを「導入して終わり」にせず、社内にしっかりと定着させるには、どうすればよいのでしょうか?
私たちが数多くの企業支援を通じて導き出した答えは、次の3つの秘訣に集約されます。
秘訣①:導入目的を明確にし、全社に共有する
最も多い失敗例は「何のために導入したのか分からない」状態を放置してしまうこと。
どれほど便利なツールであっても、現場の社員が“自分ごと化”できなければ活用されません。
導入目的は単なるコスト削減だけではなく、「電話対応の属人化をなくす」「業務の属人性を減らす」「外出先からの応答率を上げる」など、現場の困りごとを起点に伝えることで共感が得られます。
また、社内ポータルや社内報など複数チャネルで継続的に情報発信することも効果的です。
秘訣②:段階的な導入と“キーマン”の育成
いきなり全社で使い始めるのではなく、まずは一部の部署・拠点でのテスト導入(パイロット)を行うことが成功の鍵です。
その中で「この人に聞けばわかる」という社内キーマンを育成しておくと、現場の初期対応力が格段に上がります。
キーマンは単なる操作説明役ではなく、社内にZoom Phoneの“価値”を伝える推進者。
本部と連携し、改善要望を吸い上げたり、社内Tipsを発信する役割も担います。
秘訣③:導入後も“使い続けてもらう”仕掛けをつくる
導入直後の盛り上がりが落ち着いた後こそ、サポート体制が問われます。
「使われないツール」にしないためには、継続的な情報提供と社内フォローの仕組み化が不可欠です。
たとえば、以下のような支援が効果的です:
- 週1回の活用Tips配信
- チャットツールでの即時Q&A受付
- 社内FAQページの整備と周知
- 月1回の利用状況レポート+改善提案
情報が継続して届く環境があることで、社員は「使ってみよう」「相談してみよう」という前向きな姿勢を保てます。

この3つの秘訣を着実に実行することで、Zoom Phoneは単なる“電話システム”ではなく、現場の働き方を支えるインフラとして定着します。
次章からは、それぞれの秘訣についてより具体的なノウハウや実践事例を交えて深掘りしていきます。
秘訣①:導入目的を全社に“腹落ち”させるには
Zoom Phone導入の第一関門は、社員一人ひとりに「なぜこのツールを使うのか」を理解・納得してもらうことです。
この“腹落ち感”が欠けていると、どれだけ機能が優れていても現場には浸透しません。重要なのは、単に「便利になります」「コストが下がります」と伝えるのではなく、現場にとっての具体的な変化をイメージできるように伝えることです。
たとえば次のような表現です:
- ・「代表電話の取次が不要になり、1日30分のムダな対応が減ります」
- ・「外出先でもスマホで受電できるので、お客様対応のタイムロスがなくなります」
- ・「固定電話が不要になることで、ABW型のオフィス改革が加速します」
さらに効果的なのが、現場目線の事例を交えて目的を共有することです。
「他社でこんな変化があった」「この部署ではこう活用されている」といったストーリーが加わることで、導入目的は“納得感のある未来像”として社員の中に落ちていきます。

導入の背景や目的を明文化し、資料や社内ポータル、チームミーティングで繰り返し伝えることが、「納得して使ってもらう」ための第一歩です。
秘訣②:段階導入と“キーマン”育成
Zoom Phoneを全社にスムーズに定着させるには、一気に広げないことが重要です。
最初から全社展開を狙うと、「誰に聞いても分からない」「設定ミスで業務が止まった」など、現場の混乱を招きがちです。これを避けるために有効なのが、段階導入=パイロット展開です。
まずは一部の拠点・部署からテスト的に導入し、現場の声を吸い上げながら課題と改善点を洗い出します。ここで得たノウハウは、全社導入時の貴重な“現場マニュアル”になります。
そしてもう一つのカギが、“社内キーマン”の育成です。
どの現場にも、「この人が使っているなら大丈夫」「とりあえずこの人に聞けばいい」と思える人物がいます。このような“信頼される現場リーダー”をZoom Phoneの先行利用者として巻き込むことで、チーム全体の安心感と習熟度が高まります。
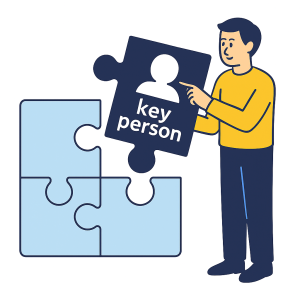
また、キーマンは単なる“操作担当”ではありません。現場での声を吸い上げて本部に伝える“現場と情シスの橋渡し役”としての役割を持たせることで、Zoom Phoneは単なるツールから“現場が頼れる仕組み”へと変化していきます。
秘訣③:導入後の継続支援が“定着の命”
Zoom Phoneが「使われないまま放置される」最大の理由は、導入後のフォロー体制が整っていないことです。
操作方法を説明するマニュアルを配っただけで終わっていませんか?
多くの現場では、ちょっとした疑問やエラーが出た瞬間に使用をやめてしまいます。
そうならないためには、使い続けたくなる“仕組み”を用意することが重要です。
例えば、以下のようなサポートが効果的です:
- 週1回、社内チャットで「Zoom Phone活用Tips」を配信
- 簡単に使える社内FAQページの設置
- 「聞いてOKな人」を明示して心理的ハードルを下げる
- 月次で活用状況をレポートし、部署ごとにフィードバック
ポイントは、「困ったときにすぐ頼れる」「新しい使い方を知れる」状態を維持し続けることです。

一方的な配信ではなく、「役立った」「便利だった」と思ってもらえる情報を届けることが、“Zoom Phoneが現場に根づくかどうか”の分岐点になります。
導入後もユーザーに伴走する仕組みこそが、本当の意味での「社内定着」を生み出すのです。
導入を“売って終わり”にしない、双日テックイノベーションの伴走体制
私たち双日テックイノベーションは、Zoom Phoneの導入支援を「設定して終わり」とは捉えていません。
むしろ、本当のスタートは「使い始めてから」。
定着し、日々の業務の中で当たり前のように使われるまでをサポートする、“伴走型の導入支援”を大切にしています。
具体的には、以下のような支援を標準でご提供しています:
- 導入前:現場ヒアリング+要件整理ワークショップ
- 導入時:初期設定・運用設計・トレーニング(管理者/一般)
- 導入後:活用サポート(Tips配信・FAQ・改善提案)
また、Zoom Phoneだけでなく、POSレジ、CRM、グループウェアなどとの連携支援も可能です。特に多店舗展開・ハイブリッド勤務など複雑な運用要件にも対応できる点が、多くのお客様から評価されています。
図:導入前〜導入後までの支援フローと伴走体制
「社員に浸透するか不安…」「最初の質問対応が面倒…」
そんな不安を抱えるご担当者様こそ、ぜひ一度ご相談ください。
導入成功のその先まで見据えた支援体制が、貴社のZoom Phone活用をしっかりとサポートします。
まとめ:定着まで支援するパートナーを選ぼう
Zoom Phoneは、単に導入するだけでは“宝の持ち腐れ”になってしまいます。
だからこそ、定着までしっかりサポートしてくれるパートナーの存在が重要です。
私たち双日テックイノベーションでは、導入計画の策定から、定着支援、他ツール連携まで一気通貫でご支援しています。
「自社に合った進め方を相談したい」「まずは試算だけでもしてみたい」
そんな方は、以下からお気軽にお問い合わせください。






